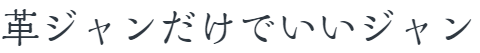職人の技術が求められる発色
革を素材として使用する際には、加工の流れで染料などを使用して革を染める行程がある。
同じ染料を使用したからといってすべての革が同じ色になるというわけではない。
染料を使用した際の色の出方というのは革によって大きく違ってくるのだ。
元々の革の色はもちろんなのだが、革の柔らかさやその個体の筋肉量・染料のバランスや気候によっても大きな違いが出てくる。
その違いを見極めるためには職人に経験値や腕などが求められてくるのだ。
革の発色は、使っているうちにも変化してくるため自分で革を育てているような感覚にもなってくる。
自分で使って自分だけの色を作っていくことができるのも、革の魅力なのかもしれない。
革のシボ
革の表面には細かい凹凸があるのはご存じだろうか。
このような革の表面の細かい凹凸のシワ模様のことをシボといい、このシボは個体によって違うたこちらも革の個性と言えるだろう。
このシボによって個々の風合いや雰囲気など生み出してくれるのだ。
牛の場合は、部位によって筋肉量が多かったり脂肪が多かったりする場所があったりと様々だ。
そのため筋肉量や脂肪量によってもシボの大きさや密度に違いが出てくる。
筋肉量の多いお尻はシボが少なく、動かすことが多い肩やお腹などの脂肪が多い場所はシボが多めになるなどの特徴があったりと、同じ個体でも部位によって個性が出てくるのが面白いところである。
天然革の血筋
革には天然と人工のものがあるが、革の表面に見られる血管のあとを血筋という。
この血筋は天然の革だからこそ楽しむことができる革の個性なのだ。
特にヌメ革などの加工があまりない革の場合は葉の模様のようにはっきりとした血筋の模様を楽しむことができる。
革の加工の過程において、この血筋を目立たないようにするという加工のケースもあるし人の好みによっては血筋が目立たないものを好むこともあるだろう。
しかし血筋は天然モノの証拠といっても過言ではないのである。
革のありのままの表情を楽しむのであれば、この血筋を楽しんでみるのも良いだろう。
今までこの部分に注目をしていなかった人も、お手持ちの革の血筋を一度じっくり見てみるといいだろう。
トラ・バラ傷
本物の動物の革にはシワやたるみなどが存在している。
このシワやたるみは染めたときにムラやシマ模様として現れる。
トラのような模様に似ていることからこの呼ばれ方がされており、皮膚の収縮が多く行われる部位によく見られる。
また、革の表面に傷跡などが残っているものをバラ傷と呼ぶ。
これは牛同士などが喧嘩して傷が残った個体に見られる特徴だ。
革となって、なお野生の生命力を感じさせてくれる特徴だ。
生のある生き物の素材だかたこそ、すべて同じというものはなく個体の個性が大きく反映される。
このような一面も革の面白さだと言えるのではないだろうか。